生成AIやChatGPTが注目されている今、「他にどんなAIがあるの?」「自分でも使えるAIってあるの?」と気になっている方も多いはず。実は、プログラミングの知識がなくても、今すぐ使えるAIツールはたくさんあります!
この記事では、初心者でも使いやすいAIツールを10個厳選して紹介します。それぞれのツールが何に役立つのか、どんなシーンで使えるのか、さらには使い方のヒントや組み合わせ方まで、たっぷりと解説していきます。
仕事、学習、クリエイティブ、日常生活…あらゆる場面であなたの「時間」と「可能性」を広げてくれるAIたちを、さっそく見ていきましょう!
ChatGPT(OpenAI)
自然な対話形式で質問や文章作成ができる人気No.1のAIチャット。
-
活用例:文章の校正、アイデア出し、英会話練習、プレゼン構成の相談など
-
補足:無料プランでも十分使える。上位モデル(GPT-4)も試せる有料プランあり。
-
応用ポイント:プロンプト(命令文)の工夫次第で、詩やスクリプト、キャッチコピーまで生成可能。
DALL·E(OpenAI)
プロンプト(文章)から画像を生成できるAI。想像を形にするツールとして注目。
-
活用例:ブログやSNSのアイキャッチ画像作成、イラストの下絵づくり
-
補足:ChatGPT ProユーザーはGPT-4(Vision)モデルを通じて、アプリ上で画像生成(DALL·E)も利用可能。
-
応用ポイント:「スタイル」「色合い」「アングル」などのキーワードで精度が大幅アップ。
Canva(AI機能付き)
世界中で愛用されているデザインツール。画像生成、文字起こし、背景除去などのAI機能が搭載。
-
活用例:チラシやバナーのデザイン、プレゼン資料の時短作成、SNS投稿のテンプレ作成
-
補足:無料プランでも豊富なテンプレが使える。Pro版でAI機能が強化。
-
応用ポイント:「Magic Write」機能でテキスト生成、「背景リムーバー」で写真の加工も簡単。
Notion AI
情報整理とAIの融合。書類や資料をサクサク自動生成する次世代ノート。
-
活用例:会議メモの自動要約、ブログ構成の草案づくり、記事のリライト
-
補足:NotionユーザーであればワンクリックでAIを起動できる。日本語も自然。
-
応用ポイント:ToDoリストや議事録作成に活用すれば、仕事効率が爆上がり!
Grammarly
英語の文法・語彙・トーンまでチェックしてくれる英文添削AI。ただし、トーンやスタイル提案などの高度な機能は有料プラン限定です。
-
活用例:メール、レポート、履歴書などの英文チェック
-
補足:ブラウザ拡張であらゆるサイトの入力に対応。ビジネス利用にも◎
-
応用ポイント:英語の「言い回し」や「自然さ」を向上させるための学習補助にも!
Teachable Machine(Google)
誰でもAI開発が体験できる!Google提供の超シンプルな学習モデル作成ツールで、教育や趣味レベルの簡易プロジェクトに最適です。商用利用や複雑なAI構築には不向きです。
-
活用例:子ども向けのAI体験、簡単な画像分類、ポーズ検出や音声分類など
-
補足:使い方次第で教育にも遊びにも応用可能。PCのカメラとマイクがあればOK。
-
応用ポイント:自作AIを使って「反応するボタン」や「ジェスチャーゲーム」も作れる!
Runway
動画制作の世界を変えた、AI搭載の映像クリエイティブツール。
-
活用例:動画の背景除去、テキストから映像生成、音声合成、カラー修正など
-
補足:無料枠あり。動画クリエイターやYouTuberに人気。
-
応用ポイント:「Gen-2」機能を使えば、1文の指示から短編映画風の動画も生成可能。
DeepL翻訳
翻訳の自然さで定評あるAI翻訳ツール。ビジネスでも学習でも大活躍。
-
活用例:外国語メールの読解、海外ニュースの翻訳、英語学習サポート
-
補足:日本語↔英語だけでなく、多言語に対応。WordやPDFの翻訳も可能。
-
応用ポイント:AI翻訳+自分の語彙力でハイブリッドな語学学習を実現!
Poe(by Quora)
複数のAIと会話できる「AIの比較・検証」に最適なマルチチャットツール。
-
活用例:AIの使い比べ、複数意見の収集、違うAI同士の比較
-
補足:無料で主要モデルが使える。ブラウザ・スマホ両対応。
-
応用ポイント:「ChatGPTとClaudeを比較したらどう違う?」という検証がすぐ可能。
Soundraw
プロ並みのBGMを、AIが自動作曲。動画やゲームにぴったりの音楽生成ツール。
-
活用例:YouTube動画、プレゼン、作業用BGM、CMやゲームのBGM制作
-
補足:著作権フリーで商用利用可能。楽曲のカスタマイズもできる。
-
応用ポイント:「曲の雰囲気」や「テンポ」もスライダーで調整できて直感的!
まとめ:まずはひとつ触ってみよう!
AIツールは、いきなり全部使いこなす必要はありません。まずは1つ、自分の興味や目的に合ったツールを選んで、触ってみることから始めてみましょう。
「思ったより簡単!」「もっと早く使えばよかった!」と感じるはずです。あなたの仕事や趣味、学びの時間が、きっとぐっとラクに、楽しくなりますよ。
そして、ひとつ使ってみると、「他のAIとも組み合わせてみたい!」という発想もきっと湧いてくるはず。
さあ、あなたの暮らしを変える“AIとの第一歩”を踏み出してみませんか?
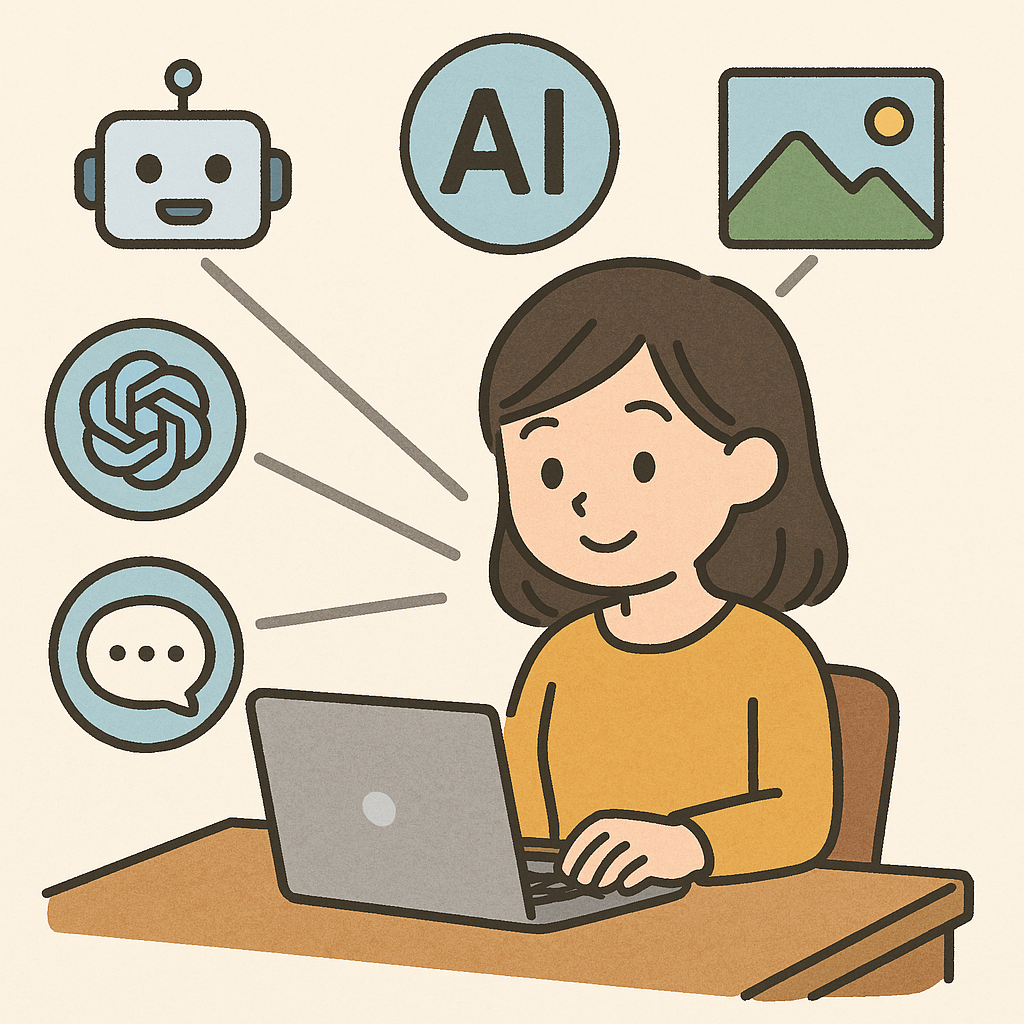


コメント